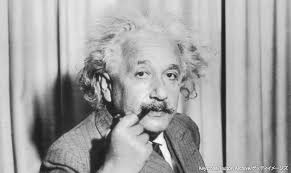アインシュタインとは?
アルベルト・アインシュタイン(1879年〜1955年)は、ドイツ生まれの理論物理学者です。**「相対性理論」**を発表し、20世紀の科学に革命をもたらしました。彼の研究は、現代の物理学や技術に大きな影響を与えています。
若き天才の誕生
アインシュタインは幼い頃から数学や物理に興味を持ち、独学で学ぶことが多かったと言われています。しかし、学校の成績はそれほど優秀ではなく、特に規則に縛られるのが苦手でした。スイスのチューリッヒ工科大学を卒業後、特許庁で働きながら研究を続け、26歳のときに歴史に残る大発見をします。
特殊相対性理論と「E=mc²」
1905年、アインシュタインは「特殊相対性理論」を発表しました。これは、時間や空間が観測者の速度によって変化することを示した画期的な理論です。
特に有名なのが、エネルギーと質量の関係を表す式
**E=mc²(エネルギー=質量×光速の二乗)**です。
この式は、「質量はエネルギーに変換できる」ことを示しており、のちに原子力発電や核兵器の理論的基盤となりました。
一般相対性理論と重力の新しい考え方
1915年には「一般相対性理論」を発表しました。それまでのニュートンの重力理論では、重力は物体同士が引き合う力とされていました。しかし、アインシュタインは、重力は空間(時空)の歪みによって生じると考えました。
例えば、太陽の周りを地球が回っているのは、太陽が時空を歪ませ、その歪みに沿って地球が運動しているからだという考え方です。この理論は、後にGPSの精度向上にも利用されています。
ノーベル賞受賞と光電効果
アインシュタインは1921年にノーベル物理学賞を受賞しました。ただし、受賞理由は相対性理論ではなく、**「光電効果の法則の発見」**によるものでした。
光電効果とは、金属に光を当てると電子が飛び出す現象です。アインシュタインは、光が「波」ではなく「粒(光子)」として振る舞うことを示しました。この研究は、後の量子力学の発展につながりました。
第二次世界大戦と原子爆弾
1933年、ナチス・ドイツの迫害を逃れるため、アインシュタインはアメリカへ移住しました。第二次世界大戦中、ナチスが原子爆弾を開発しているという情報を知り、フランクリン・ルーズベルト大統領に手紙を送りました。
この手紙がきっかけとなり、アメリカは「マンハッタン計画」を進め、広島・長崎に投下された原子爆弾の開発へとつながりました。しかし、アインシュタイン自身は戦争や核兵器に反対しており、戦後は核兵器廃絶を訴える活動を続けました。
平和活動と晩年
戦後、アインシュタインは科学者としてだけでなく、平和活動家としても積極的に発言しました。核兵器廃絶や人権擁護を訴え、晩年まで社会貢献に努めました。1955年、76歳でこの世を去りました。
まとめ
・アインシュタインは「相対性理論」を発表し、物理学の常識を変えた。
・E=mc²の式で、質量とエネルギーの関係を示した。
・ノーベル賞は「光電効果」の研究で受賞し、量子力学の発展に貢献した。
・第二次世界大戦中、原子爆弾の開発に関わる手紙を送ったが、戦後は核兵器廃絶を訴えた。
・科学だけでなく、平和活動にも尽力した偉大な人物である。
アインシュタインの理論は、今もなお科学の発展に大きな影響を与えています。彼の考え方や発見は、私たちの暮らしにも深く関わっているのです。